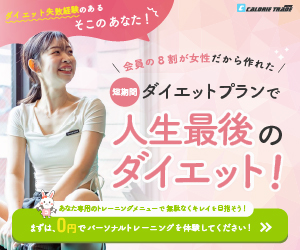随願寺
ずいがんじ □兵庫県姫路市


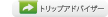


<荘厳で風格に満ちた、静寂の伽藍。>
姫路市郊外の増位山に佇む「随願寺」は、聖徳太子が創建したと伝わる播磨随一の古刹です。戦火で焼失するも、江戸時代に再建された荘厳で風格のある伽藍は、国の重要文化財に指定されています。境内は静寂に包まれ、時が止まったかのような厳かな雰囲気に満ちています。本記事では、随願寺の魅力やアクセス、そして実際に訪れて分かったオススメ情報などを詳しく紹介します。
所要時間:30〜45分(参拝・見学)
荘厳で風格に満ちた、静寂の伽藍。
隋願寺は姫路市郊外、増位山の山懐に抱かれた播磨随一の古刹。創建は聖徳太子が高麗の僧慧便をして建立させたと伝わり、その後奈良時代の名僧行基によって伽藍が整えられたと言われます。錚々たる名僧により建てられた隋願寺はのちの時代まで興隆し、一時は七堂三十六坊を有する大寺院だったそうです。
現代に見られる隋願寺は当時ほどの規模はないものの、それでも立派な堂宇が並ぶ境内は荘厳さと風格に満ちています。

姫路市郊外、増位山の山懐に佇む随願寺は播磨随一の古刹。境内は荘厳さと風格に満ちている。
森の中に突然、隋願寺の堂宇が佇む。
駐車場に車を停めて、森を抜ける小径をしばらく歩きます。寺らしい山門や玉垣で区切られた境内ではなく、森の中に突然現れるように隋願寺の堂宇が佇んでいます。16時を過ぎたくらいでしたが境内には誰1人おらず、がらんとしています。時間が止まったかのように静寂で、鳥の声と自分の足音くらいしか聞こえません。

駐車場から続く小径を抜けると、森の中に突然現れるように隋願寺の堂宇が佇んでいる。時間が止まったかのように静寂な境内。


周辺はハイキングルートになっている。


かつては七堂三十六坊を有する大寺院だった。
境内では最も古い建物、開山堂。
戦国時代までは大伽藍を有していた隋願寺ですが、1573年に兵火により全山が焼失してしまいます。その後江戸時代初期から中期にかけて復興されたのが現在の伽藍です。
なので隋願寺の堂宇の全ては江戸時代以降に再建されたものですが、様式や建築は歴史的な価値が高いものであり、その多くが国の重要文化財に登録されています。まずは最初に目にする「開山堂(奥の院)」。開山堂とは一般に山を開いて寺を建立する時に最初に建てる建物であり、隋願寺の開山堂は1641年再建、境内では最も古い建物となっています。

1573年に兵火により全山を焼失、現在の伽藍はそれ以降に再建された。その中で最も古いのが1641年に再建された「開山堂」。
唐門は重要文化財、榊原忠次墓所は独特の景観。
次に見られるのは「榊原忠次墓所」、榊原忠次とは荒廃した隋願寺を江戸時代初頭に再興した人物で、当時の姫路藩主でした。かなり立派な墓所で、正面に建つ朱塗りの唐門は国の重要文化財。1731年に建立されたものです。なぜかレンガ積みの壁に囲まれた墓には大きな石灯籠が無数に並び、奥座に位置する巨大な五輪塔が放つオーラは独特の景観を作っています。

江戸時代初頭に隋願寺を再興した人物の墓所である「榊原忠次墓所」。正面に建つ朱塗りの唐門は国の重要文化財。


榊原忠次は再興当時の姫路藩主だった。


榊原忠次の墓碑。この向こうに五輪塔が建つ。


大きな石灯籠が無数に並び建つ。


墓所と本堂の間にある巨大な石垣。
1668年に再建された、壮大な本堂。
そして本堂。本堂は1668年に再建された壮大な建物で、こちらも国の重文。訪ねた時はすでに本堂入口は閉まっており内部を見ることができませんでしたが外観は壮麗なもので、巨大な瓦屋根と睨みを利かす鬼瓦、またどっしりと腰を下ろした安定感を感じます。堂内には狩野探幽作と言われる天井画が残っており、また豪華な装飾も施されているとのこと。内陣には本尊の薬師如来像を含めた3体の仏像を一緒に納める逗子があり、年に1日だけ開帳されています。

本堂は1668年に再建された壮大な建物で、国の重要文化財。堂内には狩野探幽作と言われる天井画が残っている。


本堂は巨大な瓦屋根が印象的。


本尊の薬師如来像は年に1日だけ開帳される。
堂宇はどれも、静寂のままに佇む。
また本堂から石段を下がったところに複数の堂宇があり、経堂と鐘楼も国の重要文化財に指定されています。他にも檜の一木作りの木造毘沙門天立像(国の重文)を安置する収蔵庫や観音堂などが建ち並びます。
それらの堂宇はどれも静寂のままに佇み、隋願寺特有の荘厳な雰囲気を作り出しています。一乗寺や圓教寺とともに「播磨天台六カ寺」と称されたかつての隆盛の記憶はそっと胸に仕舞って、密やかに過ごしているようです。やはり鳥の声だけが増位山に響いています。今日が終わろうと、そして今年が終わろうとしています。その静けさは、こんなに素晴らしい寺なのに人々から忘れ去られはしないだろうかと、少し不安にさせました。

本堂から石段を下がったところに複数の堂宇が建ち並ぶ。写真は国重文に指定されている「経堂」。


鮮やかな色彩が印象的な鐘楼(国重文)。


毘沙門天立像(国重文)を安置する「毘沙門堂」。
photo.
アクセスマップと交通アクセス
■公共交通機関でのアクセス
- 姫路駅(JR・山陽電鉄)より神姫バス
系統81・82・84・86:「白国(しらくに)」バス停下車、徒歩約20〜30分(約2.2 km)。 - 播但線「野里駅」下車
徒歩約30〜40分(約1.8 km)。
■車でのアクセス・駐車場
- 播但連絡道路「砥堀ランプ」または「豊富ランプ」から車で約10〜15分。
- 境内近くに無料駐車場(40台程度)あり。大型車も可。
詳細情報
| 名称 | 随願寺 |
|---|---|
| 所在地 | 兵庫県姫路市白国5 |
| 問い合わせ先 | 079-223-7187 | 随願寺 |
| 休業日 | - |
| 料金 | - |
| 駐車場 | 無料駐車場 |
| 公式サイト | ― |
| wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/随願寺 |
| 食べログ | - |
| トリップアドバイザー | https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g298191-d20898276-Reviews-Zuiganji_Temple-Himeji_Hyogo_Prefecture_Kinki.html |
| LAST VISIT | 202411 |
※掲載のデータは当ページ更新時点でのものです。以後の変更や詳細な情報につきましては、ご自身でお問い合わせの上ご確認いただきますよう、あらかじめご了承ください。
情報更新日:2026年1月