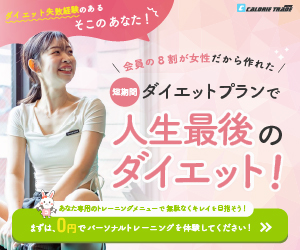賣太神社
めたじんじゃ □奈良県大和郡山市


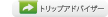


<環濠集落に鎮座する、物語の神社。>
奈良県大和郡山市の「稗田環濠集落」にある「賣太神社」は、物語の神様「稗田阿礼」を主祭神とする珍しい神社です。阿礼は古事記の編纂者の一人として知られ、謎多き人物です。境内は鬱蒼とした森に囲まれ、神秘的な雰囲気が漂っています。本記事では、賣太神社の魅力やアクセス、実際に訪ねて分かったおすすめ情報などを詳しく紹介します。
所要時間:15〜30分(参拝・見学)
環濠集落に鎮座する、物語の神社。
奈良県大和郡山市の田園風景の中に、集落全体が水を張った濠に囲まれた「稗田環濠集落」と呼ばれる町があります。戦乱の世に村の防衛のために集落全体をまるで城郭のように堀で囲ったもの。そしてそれが今もそのまま残っている珍しい景観です。
その稗田環濠集落の中にあるのが、今回ご紹介する賣太神社です。環濠集落の東南角に、森に囲まれた境内があります。

集落全体をまるで城郭のように堀で囲った「稗田環濠集落」にある神社。「めたじんじゃ」と読む。


環濠集落の東南角にあり、象徴的な存在。


創建年は不明だが平安時代の書物には記述がある。
賣太神社の主祭神は、物語の神様「稗田阿礼」。
鳥居をくぐると参道はすぐ左に曲がり、その奥に拝殿と本殿が鎮座します。境内の全てが背の高い木々に囲まれて、静寂の別世界という感じ。この日は雨が降っていたのですが、雨粒が木の葉を叩く音も聞こえてきそうです。拝殿に向かって右手前にはご神木があり、不思議なほど絡み合った根と幹が印象的です。
境内で気付くことは、「語り部の碑」という石碑があったり、読み聞かせの催しの案内があったり、どうも伝承や童話に関連がありそうだということでした。そしてそれは、賣太神社の主祭神が稗田阿礼であることに因んでいます。

境内に建つ「語り部の碑」。賣太神社は古事記の編纂者であり現在では童話の神様とされる、稗田阿礼を主祭神としている。


児童文学作家、巌谷小波を顕彰する「言霊の碑」。


元は祠があったのだろうか。
稗田阿礼は、「古事記」を編纂したひとり。
稗田阿礼は「古事記」を編纂した人物のひとりとして伝わる人物。でもそれ以外のことは詳しく分かっておらず、女性だったかもしれない、そもそも実在しなかったかもしれない、とも言われる謎の人物。ただ稗田阿礼はこの地の出身と言われ、「古事記」の伝承者として知られますし、現在は童話の神様とされてお祀りされています。毎年、稗田阿礼を偲ぶ「阿礼祭」も執り行われています。

拝殿から望む賣太神社の本殿。稗田阿礼を偲ぶ「阿礼祭」が毎年行われている。


木陰にひっそりと佇む境内社。


本殿の左側にある「鏡池」。
「賣太(めた)」に、秘められた歴史。
賣太神社の創建は定かではありませんが、平安時代中期編纂の「延喜式」に記述があり、その頃にはあったと考えられています。「賣太(めた)」というのが何を表すのがが気になりますが、ここにも稗田阿礼が関係してきます。
稗田氏は伊勢国から移ってきた一族で、元は「猿女君」という氏族でした。代々朝廷に支えていて、その一族の田圃は「猿女田(さるめた)」と呼ばれたのだそう。そののち「猿」の文字が省略されて「女田(めた)」その持ち主は「女田主」となり、現在の「賣太」に変化したのだそうです。ただし江戸時代までは「三社明神」と呼ばれており、明治時代に「賣田神社」、現在の「賣太神社」に改称したのは昭和17年になってからでした。

賣太神社のご神木。境内はスピリチュアルな雰囲気に満たされている。
環濠集落へと続く、赤い鳥居。
境内の森の中の小径を歩くと赤い鳥居があり、それをくぐると稗田環濠集落の裏通りに出ました。そこからはまるで迷路のような町並みと細い路地に。そのまま賣太神社と同じくらいひっそりとした、環濠集落の町歩きを始めることにしました。

境内北側にある赤鳥居。稗田環濠集落の町並みへとつながっている。


神社の森と接する集落の裏通り。


環濠があることで独特の景観を有する。
photo.
アクセスマップと交通アクセス
■公共交通機関でのアクセス
- JR大和路線(関西本線)「郡山駅」より徒歩約20分(約1.1 km/直線距離なら約1.14 km)。
- 近鉄橿原線「近鉄郡山駅」より徒歩約28~38分(約1.6 km)。
- バス:「稗田町売太神社前」バス停下車すぐ(約120 m)。
■車でのアクセス・駐車場
- 郡山駅から車で約5分、近鉄郡山駅から約8分。
- 神社向かい側に無料駐車場あり、5台程度駐車可。
詳細情報
| 名称 | 賣太神社 |
|---|---|
| 所在地 | 奈良県大和郡山市稗田町319 |
| 問い合わせ先 | 0743-52-4669 | 賣太神社 |
| 休業日 | - |
| 料金 | - |
| 駐車場 | 無料駐車場 |
| 公式サイト | ― |
| wikipedia | https://ja.wikipedia.org/wiki/賣太神社 |
| 食べログ | - |
| トリップアドバイザー | https://www.tripadvisor.jp/Attraction_Review-g1022856-d8150242-Reviews-Meta_Shrine-Yamatokoriyama_Nara_Prefecture_Kinki.html |
| LAST VISIT | 202410 |
※掲載のデータは当ページ更新時点でのものです。以後の変更や詳細な情報につきましては、ご自身でお問い合わせの上ご確認いただきますよう、あらかじめご了承ください。
情報更新日:2026年1月